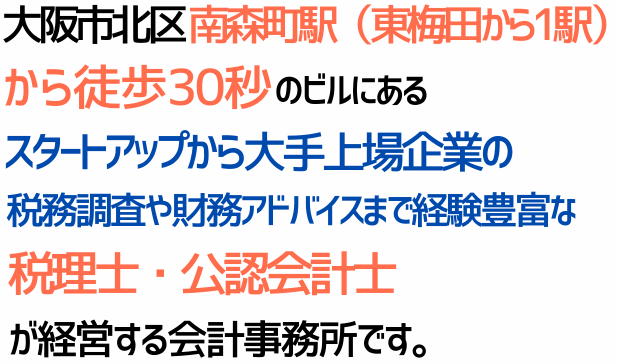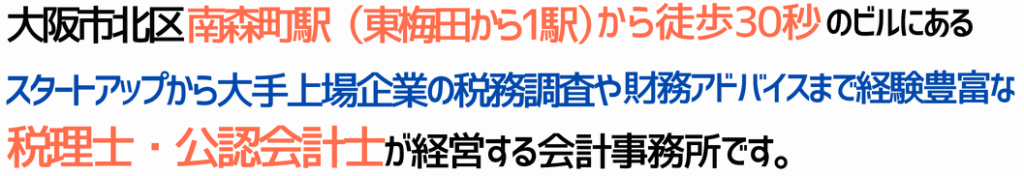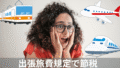役員報酬は会社にとって基本的には必要な支出ですが、法人税の計算においては会社の経費として認められないケースが沢山あります。
そのように節税ができない事態に陥らないようには以下の点に注意が必要です。
・役員報酬は基本、毎月同額で支払う
・役員報酬の変更タイミングは一定の時期
・金銭以外の現物支給でも役員報酬は役員報酬
・地位等変化や業績悪化時に変更できる場合あり
・ボーナスは金額と支払い日を事前に届出する
・それ以外の臨時の役員報酬はほぼ節税不可
・役員のプライベート費用計上は役員報酬扱い
・福利厚生費とならない役員向け支出は役員報酬
・株主総会や取締役会で会社法に沿い決定必要
・不相当に高額だと毎月同額でもダメ
これらのポイントに注意して、役員報酬で無駄に税金を増やしてしまわないようにすることが重要です。

「役員報酬の決め方・払い方どうやったら税金を節約できるのかな」
役員報酬を会社の経費として節税するために注意すべき点について以下に説明していきます。
役員報酬は変更タイミングや時期で、税金が変わる

会社の取締役や監査役など役員への報酬は取り扱いにより法人税額が変わります。
役員報酬は、変更のタイミングや時期、ボーナスの支払いかたで、法人税の計算で経費として「損金算入」できるか否かが変わるためです。
役員への報酬だけ税金計算上の扱いが違う
役員報酬に対して、従業員の方への給与とは法人税の計算における扱いが変わります。
たとえば、従業員の方への給与であれば、総額が同じであれば月次給与の変更のタイミングやボーナスの扱いで法人税の額が変わることは基本ありません。
つまり、役員報酬だけは特別な扱いとなるのです。
役員報酬の変更タイミングが節税に影響
特に、オーナー経営者の方は、基本的に自分の意思で役員報酬を支払い方も含め、決定できる立場のケースが多いですよね。
このため、月額の役員報酬を変更するタイミングやボーナスの額や時期を色々自由に調整したいと思われることもあると思います。
だからこそ、役員報酬が経費とできず法人税の額が影響を受けるリスクに要注意です。
ご自身の会社で経費とできずに節税ができない、法人税が増える支払い方法になっていないか?
是非ご注意いただければと思います。
役員報酬が経費と認められるために
それでは、役員報酬はどのような支払いかたをすれば良いのか?法人税を無駄に増やさず、税法に従った範囲で適切な水準に抑えることができるのか?
これには、大きく3つ方法があります。
この後、順番に見ていきましょう。
役員報酬を毎月同額(定期同額)で支払う

まず、1つ目の方法は、定期同額給与。
これは、基本的に毎月同額の役員報酬を支払うことです。
途中でお金が足りないと言って、勝手に役員報酬を増やして支払ったりはしません。
そのようなことをしないことで、「定期同額給与」の損金算入要件を満たせるようになります。
要件を満たせば法人税の計算上、経費・損金として役員報酬を扱い、税金を減らすことができます。
役員報酬を変更できるタイミング
それでは、いつの時期になったら役員報酬の月額を変更できるのでしょうか?
損金算入のためとはいえ、ずっと役員報酬を変えられないのは困りますよね。。
これには、毎年、役員報酬を変更できる一定の期間が用意されています。
具体的には、事業年度開始の日から3ヶ月以内のタイミングです。
この中で、継続して毎年所定の時期に役員報酬月額の改定、つまり金額変更が決定される必要があります。
定期同額は現物支給も合わせて判断
基本的に、上記の期間以外で役員報酬月額を変えては損をするとお考えください。
なお、これは金銭で支払う役員報酬が変更がなく同額というだけではありません。
なお、金銭以外で現物支給のような形の役員報酬も含めて判定する必要があります。
また、実質的な役員報酬だと税務調査官に指摘されるようなものがあれば、合わせて判定されることになりますのでご注意ください。
役員報酬を変更できる例外 – 臨時改定事由
但し、上記以外のタイミングであっても実は例外的に役員報酬の変更が認められるものがあります。
例えば、期中に特殊な状況が発生して、副社長の方が社長に就任することになるなどの場合です。
このように役員の中で、その地位や職務の内容に重大な変更があることがあります。
そのようなケースにおいては、「臨時改定事由」として定期同額給与の枠内として役員報酬の変更が認められる場合があります。
地位や職務の内容の重大な変更のタイミングで、役員報酬を改定する場合ですね。
役員報酬を減額できる例外 – 業績悪化改定事由
それ以外にも、業績悪化改定事由というものがあります。
会社のおかれている市場など経営環境が急激に変化し、会社の経営状況が著しく悪化することもあります。
この場合には、事業年度の途中に今までと同額の役員報酬を支払い続けることが急に難しくなるかもしれません。
例えば数年前、コロナウイルス感染症が急激に進んだ時期もありました。
その際、急激に業績が悪化し、役員報酬を期中で減額しなければならない会社もあったと思います。
そのように経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情があると認められる際に使えるものです。
このようなケースでは、「業績悪化改定事由」として定期同額給与の枠内、損金不算入とさせないことができる場合があります。
役員報酬のボーナスの時期・金額を事前に確定
定期同額給与の次の2つ目の方法は、事前に、役員報酬を支給する一定の時期と金額を取り決め、その内容を税務署に届出を行った上で、取り決めた通りの金額と支給日(支払日)で役員報酬を支払うことです。
いわゆる役員賞与・ボーナスを損金算入するための方法として向いているのがこの事前確定届出給与となります。
事前確定届出の提出期限
税務署への届出書の提出期限は、基本的に、事前確定届出給与の内容について株主総会等で決議をした日から1ヶ月以内か、会計期間開始の日から4ヶ月以内の、いずれか早い日となります。
但し、新たに会社設立した法人は、設立の日から2ヶ月以内が、提出期限となります。
支給日も支給金額も変えたらダメ
事前確定届出給与で、注意なのは、原則、取り決めた支給日と1日でもズレて支給したらダメですし、取り決めた金額より少しでも多くても少なくてもダメだということです。
大まかに捉えて大丈夫だと考えてしまっていると、損金算入ができないことになりますので注意しましょう。
業績連動の役員報酬
最後に、業績連動給与です。
こちらは、その名前からも、企業の業績に連動して役員報酬を支払うものであることは想像しやすいと思います。
税務上の要件がかなり厳しい
但し、法人税法における「業績連動給与」の要件は、そのイメージされる広い範囲とは異なり、かなり厳しく絞られたものとなっています。
具体的には、役員報酬を連動させる基礎となる指標が、何種類かあるのですが、それらが有価証券報告書に記載されるものに基本的に限定されています。
有報を作成しない会社は対象外
このため、有価証券報告書(「有報」)を作成しない企業にとっては、要件を満たす業績連動給与の設定自体が難しいものとなります。
このため、今回はこちらは参考としてこれ以上掘り下げずに次へ進みます。
実質的な役員報酬に注意
なお、税務上、役員報酬として扱われるものは、金銭で明確に支払われる報酬だけではありません。
実質的な役員報酬の性質であれば、同様に役員報酬として扱われます。
役員が取引先なしで高級飲食店で食事
例えば特定の役員だけで高級な飲食店で食事をするケースがあります。
それが職務を行う上で必要なものとは考えずらいような状況で、取引先も含まれていないため交際費でもないというような場合、税務調査等で実質的な役員報酬として指摘を受けるリスクがあります。
詳細はこちら→交際費、飲食費「1万円まで」本当に経費にできる?知らないと損する条件に注意。
そのような場合、役員の個人所得税の課税対象となるだけでなく、法人側でも、役員報酬が損金不算入となることで税額が増えることにつながることがあります。
特に、役員報酬を損金算入するためには、例えば定期同額給与とできれば良いのですが、予期せぬ役員報酬の発生のため定期同額とできず否認されることが考えられます。
役員の高額な出張旅費
その他にも、高額な出張旅費が旅費として認められないケースにおいては、役員報酬として扱われることになります。
詳細はこちら→出張旅費規程で節税って本当?調査で指摘される落とし穴に注意。
役員の通常の勤務時間外の食事
また、役員の通常の勤務時間外での食事の支給が福利厚生費として認められず、実質的な役員報酬として扱われることもありますので注意が必要です。
詳細はこちら→残業時の食事代は経費にできる?上限は?節税の注意点を解説
役員社宅の会社負担費用
さらに、役員社宅の制度を採用する時に、役員社宅として会社負担分が福利厚生費として認められるような要件を満たさない場合、実質的な役員報酬として扱われることになります。
詳細はこちら→役員社宅での節税と注意点。50%経費にできるって本当?

「役員報酬と経費の分かれ目は結構いろいろあるのね」
役員報酬の決め方
定款または株主総会による決定
会社法において、役員報酬は「定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。」とされています。
実務的には定款で役員報酬を決めてしまうと変更手続きが簡単でないことから、定款で決定されることは稀だと思います。
株主総会で全て決定するか、取締役会に一任する
このため、実務的には株主総会で役員報酬が決められることが多いですが、その場合にも大きく分けて2つのパターンがあります。
①株主総会で役員報酬を全役員分について決定する方法と、
②株主総会では役員報酬の総額の上限を決めておき、具体的な個別の役員報酬の決定は取締役会に一任するという方法です。
上場企業など株主数が多い場合には、一般的に上記の②の方法が採用されるケースが多いようです。
逆に株主数が少ないオーナー企業等においては、あえて2段階での決議とせずに①の方法で株主総会で具体的な役員報酬の額まで決定するケースも多いと思われます。
そして、株主総会で決定した内容については、株主総会議事録を作成し保管する必要がある点に注意しましょう。
代表取締役に決定を一任するケースもある
また、上記で、個々の役員報酬の決定を取締役会に一任するという方法については、さらに、取締役会の決議で、代表取締役に役員報酬の決定を一任することもできます。
この場合は代表取締役が個々の役員報酬を実際に決めることになります。
但し、いずれにせよ、株主総会の決議で、役員報酬の総額の上限金額を決定していることが大前提となります。
決定した上限金額を超えた役員報酬総額となるような決定を、取締役会も代表取締役も決定することはできません。
なお、取締役会で決定した内容も、取締役会議事録を作成し保管することが必要です。
取締役会で代表取締役へ一任する場合には、取締役会でその旨を決定した議事録を作成・保管することが望ましいです。
一任された代表取締役が報酬を決定する際にはその内容も書面で残しておくことが望ましいでしょう。
役員報酬の金額は職務の対価として決定する
オーナー企業等の場合には、役員報酬は、あくまでもご自身の経営されている会社からご自身の個人への資金の移管の性質にすぎないと考えられることもあるかと思われます。
この考え方自体は非常に現実的なものとはなります。
但し、税務上は、あくまでも役員報酬の金額が職務の対価として妥当か?という観点で調査時には見られることになります。
特に、以下で説明するように不相当に高額であると判断される場合には、その分の金額を経費とすることが税務調査等で否認されることにつながりますので注意しましょう。
役員報酬が高額すぎる場合は否認される
これまでは役員報酬の支払い方法(タイミングや届出など)について説明してきましたが、それ以外にも注意しなければならないポイントがあります。
役員へ支払う役員報酬の水準が「不相当に高額」であると、税務上判断される場合、やはり法人税法の観点からは損金算入ができません。
つまり、法人税が、高くなってしまうので要注意です。
そしてこの不相当に高額であるかどうかの判定は、以下の実質基準と形式基準の2つの観点から行うことになります。
実質基準で役員報酬を判定
こちらは、そもそも支給している役員報酬の水準が高すぎないかという視点です。
役員の職務内容や、その法人の収益、従業員に対する給与の支給状況、同種の事業を営む法人で事業規模が類似している法人の役員報酬の支給状況などを踏まえて検討が必要です。
その上で、その役員の職務に対する対価として相当であるかどうかを判定することになります。
形式基準で役員報酬を判定
次の形式基準ですが、簡単に説明すると、定款や株主総会で決議した役員報酬の限度額との関係で判定されます。
会社法に沿って適切に定められた役員報酬の限度額というルールを守っている役員報酬であるかどうかが判断の基準となるわけですね。
また、仮に株主総会で決議した役員報酬の総額の限度額内に収まっていたとしても、それだけでは十分ではありません。
取締役会に個々の報酬決定を一任している場合で、取締役会が決定した役員報酬の金額を実際に支払う金額が上回っている場合には、これも問題となるでしょう。
これらは上記の「役員報酬の決め方」で説明したように適切に決議を行い、しっかりと議事録を作成・保管しておくことが重要です。
両方満たさないと否認される
ですので、仮に、上記の実質基準を満たしていたとしてもこの形式基準を満たしていなかったら、不相当に高額であると税務上認定される可能性があります。
そして、その高額とされる部分の金額が、損金不算入とされることになります。
そして、形式基準を満たしていたとしても、そもそも決議した役員報酬の金額自体が不相当に高額な水準であれば、これも問題となります。
特に、形式基準に関しては、実際に決定をしていたとしても、議事録が作成・保管されていない場合には、税務調査等で客観的の証拠がないため不利な状況となります。
管理体制自体に疑念を持たれることで、それ以外の論点についても悪影響が出ることもあるので注意しましょう。
役員報酬と会社の利益のバランス
今まで法人税に与える影響の観点から、役員報酬の支払い方や水準について説明してきましたが、オーナー経営者の役員報酬については、もう一つ大事な観点があります。
それは、オーナー経営者個人の所得税と、企業にかかる法人税のバランスです。
役員報酬を増やせば所得税が上がる
役員報酬を増やす→法人税の課税所得が下がる→法人税が減る
→所得税の課税所得が増える→所得税が増える
このように、基本的には、役員報酬を増やせば、法人税が減る分、所得税が上がります。
但し、所得税は累進税率で個人所得が上がれば税率が上がり、法人税は基本的には一定で税率が推移します。
このため、トータルで税額がどうなるかという視点で検討を行うことも重要です。
できれば社会保険の影響も合わせて考えるのが良いでしょう。
役員の生活の必要資金も考える
もちろん、税務以外の面で、あまりに法人所得の方に偏って役員報酬が低すぎると、そもそも役員の方の生活がしにくくなってしまうという点もあります。
また、役員報酬が低くする関係上、無理に、個人の支出を法人の経費に混入させるということになってしまうと、結局、税務調査で問題となるリスクもあります。
但し、役員の生活という点では、役員社宅の制度も活用することがおすすめです。
詳細はこちら→役員社宅での節税と注意点。50%経費にできるって本当?
役員報酬を貯蓄すれば将来貸付もできる
役員報酬をしっかりとって、ある程度、所得税はかかるものの、社長個人がその役員報酬を貯蓄に回しておくことで、いざという時に、社長から法人へ貸付を行うことができるようにするという考え方もあります。
法人側の財務面も考える
とはいえ極端に役員報酬を取りすぎて、法人の内部留保として蓄積が全然進まないという状況になってしまったら財務面でマイナスです。
この辺りは、税金だけなく、財務も、生活も総合的に考えて検討をされるのがおすすめですね。
詳細はこちら→なぜ税務だけではダメで財務が必要か?〜財務を強くする処方箋
役員賞与・ボーナス比率が上がると、社会保険料が減る
会社が特定の役員へ支払う年間の報酬総額が同じでも、そのうち、役員賞与・ボーナスとして支払う割合が大きいと、社会保険料の年間総額が減るケースがあります。
これはなぜかというと、毎月の給与と賞与のいずれも、一定の水準以上の報酬額となると、社会保険料が頭打ちとなるためです。
その上で、毎月の給与(定期同額給与)の年間トータルと、賞与・ボーナス(事前確定届出給与)で比較すると、相対的に、賞与の方が社会保険料の上限金額が低くなっているためです。
年間1200万円の役員報酬総額の払い方を変えた例
たとえば年間1200万円の役員報酬総額だった場合に、以下のように支払ったとします。
案1)毎月同額分だけで毎月100万円支払ったとします。
これに対して、極端な例ですが、
案2)毎月同額分は毎月5万円(年間60万円)だけにして、残りを年一回の賞与・ボーナスで1140万円まとめて支払うとします。
賞与・ボーナスに役員報酬を寄せると、社会保険料トータルが減る
そうすると、案2の賞与に偏らせて1140万円を支払った方が、社会保険料の年間トータルが低くなります。
一般的な月給とボーナスの比率と比べると、かなり異なる配分となることから、社会保険料の上限を設定した際に参考にした一般的な月給とボーナスの比率の前提からズレが発生するためと考えられます。
あまり極端に行うと、税務上リスクが発生する可能性もあるため注意が必要ですが、上記のメカニズムについては理解しておくことをおすすめします。
但し月額を下げると役員退職慰労金の節税にマイナス
但し、役員退職慰労金の不相当に高額と認められない水準の計算にあたって注意が必要です。
例えば功績倍率法で行う場合、最終報酬月額が下がると、この水準自体が連動して下がってしまうという点があります。
このため、バランスを見る必要はあります。
詳細はこちら→役員退職金での節税 -「不相当に高額」で課税されないためには?
まとめ
いかがだったでしょうか。
経営者の方にとって特に気になる、役員報酬の扱いについて、ざっと大きなポイントをご説明してきました。
役員報酬の変更や支払いタイミングや届出の仕方、会社に残す利益と役員報酬の関係、賞与・ボーナスと月額報酬のバランス、などいくつかポイントとなる箇所があります。
もちろん、役員報酬は経営者の方の生活やモチベーションにも直結する部分だと思います。
このため、税務面だけを気にすることなく、トータルで事業や人生がプラスとなる方向で設定いただけると良いかと思われます。